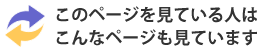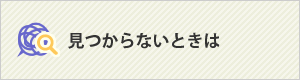今年も元気なカブトガニベビー
今年も元気なカブトガニベビー!

5月ですね。
5月と言えば、そうです!
カブトガニが活動を始めているんです!!
今年がやっと始まった気分です。
ところで、上の写真のカブトガニはみなさんのイメージしているカブトガニと少し違うのではないでしょうか?
色が白っぽいような...しっぽが短いような...
普通、図鑑などに載っている写真は成体(おとな)のカブトガニがほとんどです。
しかし、上の写真は「2齢幼生」といって、卵から生まれたカブトガニが初めて脱皮した姿なんです。
(カブトガニは、卵から生まれたときが1齢幼生、1回脱皮すると2齢幼生、もう1回脱皮すると3齢幼生といった具合に成長していきます。)
↓ちなみに1齢幼生にはまだ尾剣(しっぽ)はないよ↓

前体幅( )は、1齢幼生で6mmで2齢幼生で9mmほどですので、まさにカブトガニベビーと呼びたくなるサイズです。
)は、1齢幼生で6mmで2齢幼生で9mmほどですので、まさにカブトガニベビーと呼びたくなるサイズです。
ところで、誤解があってはいけないのでいっておきますが、このカブトガニベビーたちは今年生まれたわけではありません。
6月から7月頃に笠岡では産卵します(そして50日ほどでふ化します)ので、元気に2齢幼生に脱皮しているカブトガニはみんな平成27年に生まれたベビーたちです。
脱皮殻と1齢幼生と2齢幼生
さて、今回は脱皮したカブトガニをより分ける作業を少しご紹介したいと思います。
↓泥とカブトガニが入った容器から、網でカブトガニを取り出しました↓

ゴミのよう(失礼)にフヨフヨしているのがカブトガニです。
↓アップにすると...↓

よかった。ゴミじゃなかった。
この中から脱皮殻と1齢幼生・2齢幼生に分けて、脱皮殻は標本に、1齢幼生と2齢幼生は別のバット(容器)に移して飼育します。
1齢幼生と2齢幼生を別に飼育する理由は、1齢幼生はエサを食べませんが、2齢幼生になるとエサを食べるようになるからなんです。
↓脱皮殻(これで100個あるかないかくらい)↓

多いものだと1つのバットに1000匹ほど飼育しているので、より分けるのは大変な作業です。
こうしてより分けられた2齢幼生は、毎日モリモリと元気にエサを食べています。
↓エサを食べてご満悦(?)な2齢幼生↓

「なんか鼻みたいなところが赤くなってない?」
と思ったカブトガニに興味津々なそこのあなたは、こちらでカブトガニの体を学んでみてください。
→エサを食べると赤くなる?
ところで上の写真のカブトガニはまだ色が薄いですが、毎日エサを食べて少しずつカブトガニらしい色に近づいていきます。
↓あと10日でこれくらいの色合いになります↓

元気に育って、早く3齢幼生に脱皮してほしいものです。
3齢幼生は2齢幼生と比べて尾剣(しっぽ)が長くなって、よりカブトガニらしくなってかっこいいんですよ!
それでは、いつか放流するカブトガニですが、愛情をもって飼育していきます。