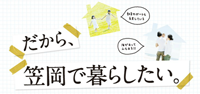本文
第3次笠岡市産業振興ビジョンについて
第3次 笠岡市産業振興ビジョンを策定しました
笠岡市では,計画的に産業振興を図り,豊かで活力ある笠岡市を創造するため,2014(平成26)年3月に初めて「笠岡市産業振興ビジョン」を策定し,2019(平成31)年に改訂を行いつつ,関係機関等との連携により,「企業誘致」「地元中小企業振興」「観光振興」を三本の柱として,諸施策に取り組んできました。
そうした中,近年のまちづくりの進展や企業の景況感など社会経済情勢が下降から上昇基調への変化や,国を挙げて積極的に進めているSDGs,デジタル化のさらなる加速,市内企業の「人手不足」感の高まり,障がい者雇用の推進,インバウンドによる観光への影響などをふまえ,今回本市経済のさらなる発展に向け,産業振興ビジョンの見直しを行いました。単なる計画策定に終わらない「実効性」と「継続性」のあるものとし,時代の潮流に対応した地域が一体となって持続可能な地域経済の確立を目指していきます。
そうした中,近年のまちづくりの進展や企業の景況感など社会経済情勢が下降から上昇基調への変化や,国を挙げて積極的に進めているSDGs,デジタル化のさらなる加速,市内企業の「人手不足」感の高まり,障がい者雇用の推進,インバウンドによる観光への影響などをふまえ,今回本市経済のさらなる発展に向け,産業振興ビジョンの見直しを行いました。単なる計画策定に終わらない「実効性」と「継続性」のあるものとし,時代の潮流に対応した地域が一体となって持続可能な地域経済の確立を目指していきます。
計画期間
2024(令和6)年度から2028(令和10)年度までの5年間
基本理念
「人口減少社会に対応し 新たな産業連関構造を目指すまち笠岡」
本市の社会動態は,改善傾向にありますが,それを上回る自然動態の減による人口減少が続いている本市の状況において,人口問題と地域経済活動は,切れない関係にあります。人口減少期においても,地域で心豊かに生活できる環境を目指します。
キャッチフレーズ
「稼ぐ力が育つまち笠岡」
戦略方針
第1の柱:企業誘致(外発的産業振興)
県営工業団地である「笠岡港(港町地区)工業用地」の分譲が順調に進み,令和5年に完売となりました。また,岡山県内においても,県南部を中心に工業用地が不足している状況です。そこで,新たな用地整備のため産業系土地利用の検討及び住宅整備促進に関するサウンディングやアンケート調査を実施し,市内の土地利用の方針を今後も模索していきます。
本市は倉敷市や福山市,井笠圏域を含む人口100万人都市圏の中心に位置し,地理的に非常に高いポテンシャルを有しています。また,令和7年度末頃に完成する,国道2号バイパスや山陽自動車道篠坂パーキングエリアのスマートインターチェンジにより,広域交通の利便性が大きく向上することが見込まれており,今後,企業の事業拡大や企業が用地を探しているといった要望に適切に対応するために,行政にしかできない農業振興地域の除外や土地利用規制の変更に係る措置を中心とした支援や事業用地造成促進奨励補助金の活用による民間活力でオーダーメイド方式の工業用地の造成を進めます。
本市は倉敷市や福山市,井笠圏域を含む人口100万人都市圏の中心に位置し,地理的に非常に高いポテンシャルを有しています。また,令和7年度末頃に完成する,国道2号バイパスや山陽自動車道篠坂パーキングエリアのスマートインターチェンジにより,広域交通の利便性が大きく向上することが見込まれており,今後,企業の事業拡大や企業が用地を探しているといった要望に適切に対応するために,行政にしかできない農業振興地域の除外や土地利用規制の変更に係る措置を中心とした支援や事業用地造成促進奨励補助金の活用による民間活力でオーダーメイド方式の工業用地の造成を進めます。
第2の柱:地元中小企業振興・起業支援(内発的産業振興)
地元中小企業が抱える問題点・課題に対応した支援の展開や,事業者が新たに取り組むビジネスの支援,起業家精神が旺盛な人材が起業し,成長しやすい環境を整えること等によって地元中小企業の振興を図ります。
地元企業を強化し,域外からのマネーを獲得し,地元自給率を高めマネーを域内で循環させる域内産業の振興を目指します。
農業については,農産物を生産・出荷するだけでなく,加工・流通とつなぎ,付加価値を高める取組を展開するとともに,県内屈指の経営規模を誇る笠岡港干拓地の農業では,環境と調和した持続的な生産ができるように環境負荷に配慮した循環型農業の実現に向けて支援します。水産業については,本市の豊かな海を再生・維持するため,稚魚の放流の支援・養殖等により水産資源の回復・再生を図ります。
地元企業を強化し,域外からのマネーを獲得し,地元自給率を高めマネーを域内で循環させる域内産業の振興を目指します。
農業については,農産物を生産・出荷するだけでなく,加工・流通とつなぎ,付加価値を高める取組を展開するとともに,県内屈指の経営規模を誇る笠岡港干拓地の農業では,環境と調和した持続的な生産ができるように環境負荷に配慮した循環型農業の実現に向けて支援します。水産業については,本市の豊かな海を再生・維持するため,稚魚の放流の支援・養殖等により水産資源の回復・再生を図ります。
第3の柱:観光振興(交流による経済活性化)
交流人口の拡大のために,「笠岡市観光振興ビジョン」と整合を図り,地域資源を活かした観光産業の振興を推進します。(1)観光まちづくりと商品化,(2)ブランド化・情報発信,(3)受入環境・体制の施策体系による,ブランド力の強化と魅力ある観光資源の発掘と保存,効果的な情報発信とプロモーション等により,「観光地としての笠岡の地位の確立」を推進します。「住んでよし」のまちだけでなく,「訪れてよし」のまちを地域一体となって創り,稼げる地域づくりを目指します。
具体な取組としては,笠岡湾干拓地エリアの道の駅笠岡ベイファームのリニューアル,笠岡諸島エリアの日本遺産ストーリー「せとうち石の島」の推進,周遊エリアの地域資源(自然,景観,食)の磨き上げ等とともに,ブランド化・情報発信に努めて各エリアのイメージ定着を図ります。また,移動手段や環境整備だけではなく,担い手の発掘や育成に努めます。
具体な取組としては,笠岡湾干拓地エリアの道の駅笠岡ベイファームのリニューアル,笠岡諸島エリアの日本遺産ストーリー「せとうち石の島」の推進,周遊エリアの地域資源(自然,景観,食)の磨き上げ等とともに,ブランド化・情報発信に努めて各エリアのイメージ定着を図ります。また,移動手段や環境整備だけではなく,担い手の発掘や育成に努めます。
詳しい内容は,添付ファイルをご覧ください。