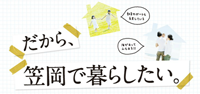本文
農地に太陽光発電装置を設置する場合の取扱について
農地を耕作以外の目的で使用する場合には農地転用の申請が必要です。その中でも,太陽光発電を設置するための農地転用の申請についての笠岡市農業委員会での取扱については,次のようになっています。
営農型以外の太陽光発電設備を設置する場合
農地の種別によって転用できるかどうかが変わってきます。農地の地番が分かったら,事前に農業委員会事務局にご相談ください。
・ 農用地区域内農地(いわゆる「農振」) 転用不可
・ 第1種農地 転用不可
・ 第2種農地 第3者の転用は不可
※ 所有者本人またはその家族等が転用する場合で,
申請地しか設置することができない場合は,事前に
農業委員会の現地調査を行い,転用しても良いと
判断された場合のみ,申請可能。
・ 第3種農地 転用可(第3者の転用も可能)
営農型発電(ソーラーシェアリング)の場合
農地に支柱を立てて,営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合は,上記と取扱が異なります。この場合も,まずは農業委員会で現地確認をさせていただきますので,事前にご相談ください。
また,営農型発電の場合は,下部の農地の営農が行われない場合又は発電事業が廃止される場合は,支柱を含む当該設備を速やかに撤去し,農地として利用できる状態に回復することになります。
◎許可要件
営農型発電の場合の転用については,次のような要件があります。
◆ 一時転用であること。
3年以内または10年以内の一時転用の申請となります(恒久転用はできません。)
※10年以内の一時転用ができるのは,認定農業者が行う場合等,対象が限られています。
◆ 容易に撤去できるものであること。
転用面積は農地のうち支柱(または基礎)部分のみとなります。構造は単独基礎や地面に
打ち込むだけのものなど,容易に撤去できるものでないと認められません。
※ 営農の適切な継続が行われていないと判断された場合,発電装置を撤去しなければなりません。
◆ 農業用機械等を効率的に利用して営農するための空間が確保されていること。
支柱の高さは最低地上高が2m以上であること等,支柱の高さや間隔,パネルの角度や間隔等が
営農できるようになっている必要があります。
◆ 周りの農地の効率的な利用,排水施設の機能等に支障を与えないこと。
◆ 撤去するのに必要な資力及び信用があること。
転用申請時には,撤去費用についての資金証明も必要になります。
◆ 電気事業者と転用事業者が連系にかかる契約を締結する見込みがあること。
◎申請添付書類
転用申請時に必要な書類として,通常の添付書類の他に次のものが必要になります。
◆ 営農型発電設備の設計図
◆ 下部の農地における営農計画書
◆ 営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる
関連データ(遮光率・日照量の確保や収穫量の見込みの根拠資料等)
◆ 必要な知見を有する者の意見書又は取り組んでいる者の事例
◆ 設置者と営農者が違う場合は,設置者が費用を負担することを基本として合意されていることを
証する書面
※ その場合,支柱に係る転用許可と,下部の農地に地上権又は貸借や同様の権利を設定するための
3条申請を併せて行うことが必要
◆ 現地調査の結果によっては,周囲の農地所有者の同意書等を求めることがあります
※「営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の
見込書」様式はこちら [Wordファイル/59KB]
◎報告
営農型発電で転用許可を受けた場合,下部の農地で生産された作物の状況を,収穫した年の翌
年の2月末日までに許可権者に報告しなければなりません。
また,報告内容が適切かどうかについて,必要な知見を有する者の確認を受けなければなりません。
※「営農型発電設備の下部の農地における農作物の状況報告書」の様式はこちら [Wordファイル/39KB]
◎転用期間の満了
満了時には,改めて一時転用申請が必要です。その際には,再度許可要件の確認を行い,下部の農地の
営農の状況について調査されます。
※ 適切な営農の継続が確保されていない場合は,発電装置を撤去する必要があります。
◆ 適切な営農の継続が確保されれいないと判断されるもの
・営農が行われない場合
・下部の農地の反収が,同じ年の地域の平均的な反収と比較して概ね2割以上減少している場合
・下部の農地で生産された作物の品質に著しい劣化が生じている場合
・農作業に必要な農業機械等を効率的に利用することが困難である場合
◎営農型発電に関する取組支援等(農林水産省HP)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html<外部リンク>