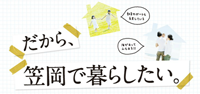本文
腸管出血性大腸菌感染症に要注意!!
腸管出血性大腸菌感染症注意報 発令中!
岡山県内で腸管出血性大腸菌感染症の発生が増加しており,今後もこの傾向が続く可能性があることから,「腸管出血性大腸菌感染症注意報」が岡山県から発令されています。(令和7年7月30日発令)
予防方法
- 調理前、食事前、排便後、動物を触った後等は手をよく洗いましょう。
- 台所は清潔に保ち、まな板、ふきん等の調理器具は十分に洗浄消毒しましょう。
- 生鮮食品や調理後の食品を保存するときは、冷蔵庫(10℃以下)で保管し、早めに食べましょう。
- 食肉など加熱して食べる食品は、中心部まで火を通すとともに、焼き肉などの際は、生肉を扱うはしと食べるはしを別々にしましょう。
- 乳幼児や高齢者等、抵抗力の弱い人は、生や加熱不十分な肉を食べないようにしましょう。
気になる症状があるときは、早めに医師の診断を受けましょう
- 主な初期症状は、「腹痛」、「下痢」などで、更に進むと水様性血便になります。
- 溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症等の重篤な合併症を発症することもあります。
患者からの二次感染に気をつけましょう
- 二次感染を防止するため、患者の便に触れた場合は、手をよく洗い消毒しましょう。
- 患者が入浴をする場合は、シャワーのみにするか、最後に入浴するなどしましょう。
- 患児が家庭用ビニールプールで水浴びをする場合、他の幼児とは一緒に入らないようにしましょう。
- なお、患者が衛生に配慮すれば、二次感染は防止できますので、外出の制限等は必要ありません。
◎パンフレット

○腸管出血性大腸菌感染症注意報発令中(岡山県) [PDFファイル/780KB]
◎関連リンク
〇岡山県感染症情報センターホームページ<外部リンク>
○厚生労働省(食中毒) ホームページ<外部リンク>
○腸管出血性大腸菌Q&A(厚生労働省)<外部リンク>