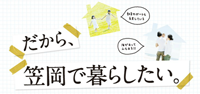本文
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
(長期譲渡所得の100万円控除)
1 特例措置の概要
この特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」といいます。)の譲渡をした場合について、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
令和5年度税制改正において、令和2年度税制改正において創設された低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置の適用期限が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が引き上げられました。
2 特例措置の適用条件
以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが可能です。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1または2の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。- 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
3 特例措置の手続きの流れ
- 売主が物件所在地の市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請
- 市区町村が確認を実施し、低未利用土地等確認書を発行
(申請書の提出から、低未利用土地等確認書の交付まで1~2週間程度かかりますのでご了承ください。) - 管轄税務署にて確定申告 (低未利用土地等確認書を提出)
- 特例適用
4 低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
|
|
必要書類 |
|
低未利用土地等であることの確認 |
|
|
譲渡後の利用についての確認(※3) |
|
|
その他の要件の確認等 |
申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(※1)
申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても確認可能。
(※2)
支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3)
いずれも提出できない場合に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について宅地建物取引業者が証する書類 [Wordファイル/63KB]によっても確認可能。
5 低未利用土地等確認書申請の窓口
笠岡市総務部税務課
電話:0865-69-2116
Fax:0865-63-6130
Email:zeimu@city.kasaoka.lg.jp
〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地の1