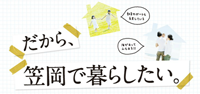本文
国 登録有形文化財(建造物) 長鋪家住宅
長鋪家住宅 主屋と内門
■名 称:長鋪家住宅(ながしきけじゅうたく)
■登録建物:主屋・内門・内蔵
■所在地:笠岡市神島
■所有者:個人
■登録年月日:2024(令和6)年3月6日
長鋪家住宅は、神島北側の汁方地区の丘陵上に位置しています。笠岡湾干拓事業が行われる以前は、眼下に海が一望できました。
長鋪家は江戸時代の末期から神島の庄屋を務めた名家で、塩田の開発や廻船業で財をなしました。敷地内に天保2年(1831)の銘が刻まれた石灯籠があることから、少なくともそれ以前から屋敷があったと考えられています。
主屋は元々,江戸時代末期に建築されたと考えられています。建築当初は、土間、茅葺き屋根など農家の特徴をもっていました。大正時代に屋根が瓦葺きに改修され、増改築が行われてきましたが、今でも柱や差し鴨居、梁の一部などに江戸時代の構造が残っており、当時の家屋の形式が想定できます。特筆すべきは、大正期に整備された客座敷です。屋根には寺社建築で使われる形式が用いられ、室内の床の間には貴木が使われ、客をもてなすための特別な空間が整備されました。
内門(御成門)も大正時代に改築されたもので、屋根の部分には主屋と同じく寺社建築の形式が取り入れられ、特別な接客空間への導入部としてふさわしい意匠となっています。地域の裕福な名士がしつらえた質の高い住宅として、文化的に高く評価されています。
江戸時代末期に建てられた内蔵には穀物を貯蔵する設備が残っており、建築当時は穀倉として使われていたと考えられます。また、大正時代に改修された屋根は、大棟などに主屋と同様の模様を持っており、意匠性も評価されています。

内蔵
※長鋪家住宅は、個人の住宅です。通常は一般公開されておりませんのでご注意ください。
※イベントなどの開催時のみ敷地内を見学できます。(イベントの情報は「長鋪邸」のfacebookから確認できます。)