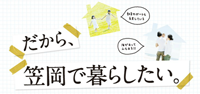本文
貫閲講堂
貫閲講堂について
社会教育施設「貫閲講堂」
所在地 笠岡市笠岡 笠岡市立笠岡小学校敷地内
建設年 昭和17(1942)年
貫閲講堂の使用休止について
学校や地域住民の皆さんにご利用いただいてきた貫閲講堂につきまして,近年老朽化により補修工事がふえたことから,施設の劣化状況を把握する調査を実施しましたところ,柱の損傷が判明しました。
そのため,令和元年8月から,当面の使用を休止しております。ご迷惑をおかけしますが,ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
貫閲講堂の歴史
笠岡小学校の敷地内に建っている貫閲講堂は,旧「笠岡町男子・女子国民学校」時代の昭和17年(1942)7月8日に落成しました。その規模は,延べ233坪,収容人員3,200人という,当時としては堂々たる建物であり,木造二こう式トラス構造という技術を駆使することによって,この空間を実現しています
講堂の建設費用(77,500円)の大部分を笠岡町に寄附した佐藤貫一氏は,明治24年(1891)笠岡東本町に生まれ,中国に渡って製粉・酒造・醤油会社を経営し,南京商工会議所会頭や南京居留民国民会議議長など,財界人として重要な仕事に携わった人物です。寄附に当たって,多くの人が利用できる建物を提案されました。そのため,貫閲講堂は,単に学校施設であるだけでなく,町民全体にとって,各種の集会や行事を行う,いわば公民館や市民会館のような役割をも担ってきました。
笠岡市民会館がオープンした昭和49年(1974)以後も,引き続き入学式や卒業式などの学校行事,地域の行事等で利用されてきました。
貫閲講堂の劣化状況
・令和元年度~2年度に劣化調査・耐震診断をしました。
・柱のシロアリ被害が判明しました。(20本ある柱のうち,健全・被害小の柱は3本のみ。)
・建築基準法の想定する大地震(地震6強~7程度)に対して「倒壊する危険性が高い」と診断されました。
・令和元年8月から立入禁止としております。
貫閲講堂の今後の取り扱いについて
貫閲講堂の今後の取り扱いにつきましては,歴史性やシンボル性,まちづくりにおける可能性を考慮しつつ,財政的な問題,地域の温度差,子どもたちの安全性等を総合的に考慮しながら,方針を決定して参りたいと考えております。