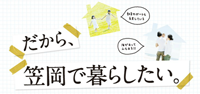本文
平成29年度高梁川流域デジタルアーカイブを作成しました。
高梁川流域デジタルアーカイブ事業
高梁川流域圏の7市3町(新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市・倉敷市)が協力して取り組む高梁川流域連携中枢都市圏事業の一つとして、圏域の映像記録を作成するための「高梁川流域デジタルアーカイブ事業」を行っています。
高梁川流域デジタルアーカイブHP<外部リンク>
高梁川流域デジタルアーカイブ事業
1 事業内容
高梁川流域圏、それぞれの土地に根づく風習・自然・建築・工芸・食文化などを人に焦点を合わせて、圏内の人には地域への愛着や誇り、圏外の人には憧れや興味を抱かれるような映像記録として作成します。
単に物を紹介するだけでなく、関わる人やそのものに関する物語、想いが伝えられるものにします。
2 映像
映像は1本5分で、1本に付き1つの題材を紹介し、年間20本作成します。
3 公開
作成した映像については、高梁川流域連盟の「高梁川流域Map」を含め倉敷市ホームページやYoutube等で公開します。
平成29年度作成作品
●長福寺裏山古墳群<外部リンク>
南から七つ塚古墳群、双つ塚古墳、仙人塚古墳、一つ塚古墳、仙人塚古墳、東塚古墳を総称して長福寺裏山古墳群と呼んでいる。このうち、双つ塚古墳と東塚古墳は前方後円墳である。発掘調査により、埴輪や須恵器、鏡・馬具などの金属製品などが見つかっている。5世紀から6世紀にかけて、勢力を拡大させた豪族の墓と考えられている。笠岡市指定史跡。出土品は笠岡市立郷土館で展示している。
●小田県庁跡<外部リンク>
現在の笠岡小学校の敷地は、明治時代の小田県庁跡である。笠岡小学校のシンボルともいえる白壁の門は、小田県庁の正門だった建物である。この門は明治時代、現在の岡山市にあった戸川陣屋の長屋門を移してきたもので、瓦には戸川家の家紋である三本杉がデザインされている。小田県は、廃藩置県によって明治5(1872)年に誕生した、備中国と備後国東部を含む大きな県だった。岡山県に統合される明治8(1875)年まで、笠岡に県庁が置かれていた。笠岡市指定史跡。